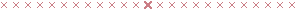目の前に突き出されたおちんちんに、わたしは唇を添える。
ベッドに座った彼の前に両膝をついて、股間に顔を埋めるの。
おちんちんを向けられたら、しゃぶらなくちゃいけない――だって、雪子は進くんのペットだから。

「おいしい?」
口唇の中で舌を動かし始めたわたしに、進くんは優しく問いかけてくる。
「はい……進くんのおちんちん、とってもおいしいですぅ」
固くなってきたおちんちんの先端を舐め上げると、彼が小さくうめいた。その
抑え気味の声から、感じていることを表に出すのが少々恥ずかしいことを悟る。
わたしが見つけた、彼の可愛い部分のひとつ。
「もっともっと、感じてください……雪子でキモチよくなってくださぁい」
わたしは先っぽをくわえて、舌先で尿道を刺激した。
「うぁっ……」
進くんは息を荒くさせながら、わたしの頭を押さえる。もっと深くしゃぶっ
て欲しいという意思表示だ。
(雪子のフェラチオを、もっと感じたいって思ってくれてるんだ……)
カラダが熱くなってくる。知らぬ間に乳房に手が伸びて、自分で乳首をこねて
しまう。床についていた左手も、太股の間でもぞもぞと動き始めていた。
「あぅんっ……」
濡れてる。
おちんちんをしゃぶりながら、あそこがよだれを垂らしているのがわかる。
もっと感じたい。進くんと一緒に、もっとキモチよくなりたい。
口唇に包まれている亀頭が、ぴくぴく震えてきた。
「雪子……もう出ちゃいそうだよ……」
「飲ませて……進くんの精液、雪子に全部飲ませてぇ……」
口唇で太幹をしごきながら、亀頭を舌で舐めまわす。
水気を含んだ、いやらしい音を微かに響く。それ以外は聞こえない。ここは進くんのお部屋。雪子と進くんだけの、甘い空間。
「んっ、んぅっ……」
彼のうめき声だけでなく、わたしも思わず声を漏らしてしまっていた。声と一
緒に気持ちまで弾ませて、恋人の男根を頬張るという淫らな行為に夢中になって
いた。
舌先を尿道に押しつけると、わたしの頭を押さえていた彼の手に突然力がこも
った。
「……うぅっ、うぁっ!」
びくん、とおちんちんが震えた。のどの奥に精液が次々と射ち込まれる。
こくん、こくんと熱い塊を飲み込む。わたしのために出してくれた大切な精液
を、一滴も外に漏らしたくない。だって、これは雪子へのごほうびだもの。
律動を繰り返す男根に両手を添えながら、わたしは両眼を閉じて射精を受け入
れた。
一度止まっても、舐めてあげるとまた出してしまうのが可愛い。欲張りなわた
しは尿道に残っている分も優しく吸い出していた。
「……全部、飲んでくれた?」
「はい。おいしかったです」
口唇からおちんちんが離れる。精液と唾液が絡まった糸が緩み、零れる。
カラダが震えている。彼の射精を受け止めて、奥の方が熱くなっていた。
「んはぁっ……」
まだ、わたしの視線は進くんのおちんちんに釘付けだった。
まるで浮かんでいるような気分で、細かい思考ができない。自分の股間をこね
あげる指の動きが、知らぬ間に大きくなっていることにも気づいていなかった。
そんなわたしの左腕を、彼の手が抑えつける。
「あっ……」
「僕の許しなしに、勝手に弄るなんていけない娘だ」
2004.6.10
|